午前中に備中松山城を制覇した私たちは、午後は同じ高梁市内の吹屋に向かいました。
吹屋とは明治以降、三菱の吉岡銅山の隆盛に沿って栄えた街。
映画、金田一耕助が活躍する【八墓村】のロケ地にもなりました。
毛利氏との戦に敗れた尼子氏の残党落人が、村人に寄って惨殺された・・・祟り・・・を扱った映画でしたが。
ドロドロした映画のイメージとは違って、観光地として整備された明るい街並みです。
なぜこの街に多くの観光客が押し掛けるのか?
この街並みの特徴は・・・銅を製錬した時に副産物として出て来る【酸化鉄】が、ベンガラと呼ばれる染料として街並みの色になっているのです。
どういうところに使われるのか・・・壁や木部、屋根瓦・・・などで、防腐剤・防虫剤などとして使われました。

この薄赤い色がベンガラの色です。
壁が少し赤みを帯びたり、奥のお宅の屋根瓦もベンガラ色になっています。
もちろん衣類の染料だったり、現在では焼き物の釉だったり。
現在、観光客相手に何かを贖うお店の暖簾は、申し合わせでベンガラ色にしているようです。
変わったところでは・・・北アルプス後立山(うしろたてやま)連峰の白馬(しろうま)岳の大雪渓では、安全なコースの道しるべとして雪の上に赤く蒔かれています。
グランドに石灰で線を引く・・・のと同じ意味合いで、白い雪渓では赤いベンガラが使われています。
余談ですが白馬岳は【はくばだけ】・・・ではなく【しろうまだけ】と言います。
インバウンドで活況を呈する町の名前は【はくば】なのに・・・不思議です。
話を戻して
ベンガラは関西や九州などで多く利用されて、吹屋の商人は多くの財を成しました。
代表格が【片山家】で、住居を公開していますが、見学はしませんでした。

赤く染まった街並み同様に人気を集めるのが吹屋小学校。
明治30年代に築造され、平成24年に閉校となるまで現役最古の木造校舎として使われてきました。
最盛期の生徒数は350人も在籍したそうです。
現在は明治時代の洋式建物として、岡山県の文化財に登録されています。
10億円もかけてリフォームしたそうです。
隣の敷地に中学校もありましたが、今近代的なホテルになっています。

実は・・・これ・・・観光案内用電気自動車から写しています。
歩いて街並みに入って行くと・・・電気のバスがやってきて、おじさんが「乗らない?」と。
一旦、駐車場に戻るけど良かったら乗らないか?
いくらですか?
無料ですよ!
午前中にお城に登った妻は・・・足がパニックでしたから、渡りに船でした。
おじさん・・・駐車場に戻ったのは、トイレでした。
ボランティアで2年ほど、このバスを運転しながら乗車した方にガイドを。
コースはほぼ街並みを一周してくれます。
ベンガラのこと、小学校のこと、片山家のこと・・・夫婦で歩いても知りえない情報が次から次と。
楽しみながら街を観ることが出来ました。
欠点はバスに乗って【楽(らく)】を知ったら、途中に興味のあるものがあっても・・・降りようとしない二人。
一度も降りずに街並みを一周して、駐車場に戻りました。
おじさんと記念写真。

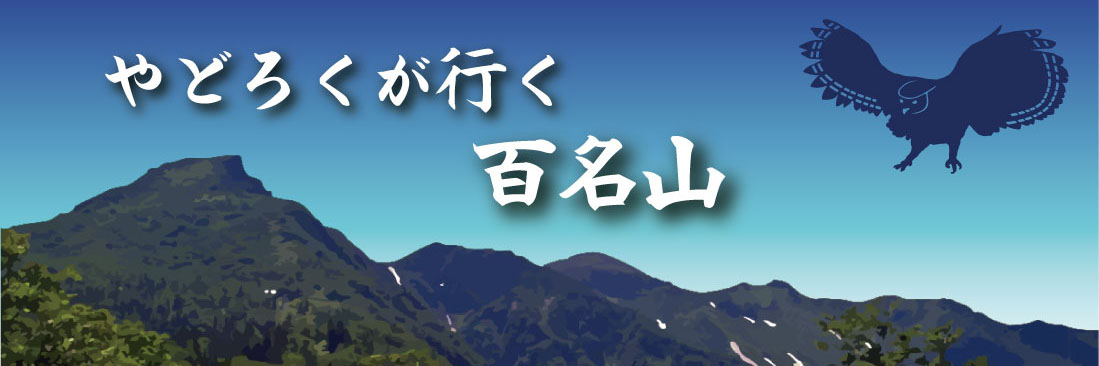


コメント