子供のころは野球少年だった私。
でも巨人と阪神の江川・小林トレード問題以降、野球の興味は薄れていて。
テレビ中継の野球なんて、とんと観ることはありませんが。
高校野球だけは・・・ゲームの純真・ひたむきさが好きで良く見ていました。
だから過去の名勝負などを語らせたら・・・話しは長くなります。
でもやはり星稜松井への4連続フォワボールに、高校野球の将来を見た気がして・・・やはり心が離れて。
よほどやることがない時しか観ません・・・【勝ち】至上主義の私立高校の姿勢には辟易しています。
高校野球はそもそも【教育の一環】で、勝つことも大切だけれど【負け】からしか学べないことも大事にすることを教えるべきなのです。
あの徳島の池田高校、さわやかイレブンで一時期を席巻した名将蔦監督は常々【子供たちにとっては負けることの方が大切だ】と言っていました。
【負けて良かった】と・・・けっして負け惜しみではなく、その言葉は子供たちへの愛情があふれていた。
常勝監督で勝負にかけては【攻めだるま】と言われた方の言葉とは思えない、実に意味深い言葉である。
子供たちにとって優勝も得るものがあるだろうが、子供たちの将来にとって負けて知ることの方が大切・・・と。
甲子園で勝つも敗けるも、教育の一環だと言うことを忘れてはいけない・・・と言うメッセージと私はいつも思っていました。
確かに勝たなければ【クビ】になるかもしれない私立の監督にとっては、生徒を殴ってでも勝ちたい気が起きるでしょう。
甲子園出場が学校の存続にかかわる最近の少子化もあり・・・事件を隠蔽したり、有名監督を招聘したい気も理解できます。
しかしそんな時勢に・・・今日、素晴らしいチームに胸を熱くしました。
随所に・・・やっぱり所詮は高校生・・・と思えるミスもありましたが、それを取り消しにするひたむきなプレー。
一方、必ずしも純真な高校生か? と疑わせる高校球児も。
全ては監督の姿勢だと思われる・・・高校生らしくないシーンがいくつかありました。
ハーフスイングで三振を取られたバッターが、主審に何かを話していましたが・・・ストライク・ボールは主審に従うべき。
スイングの確認をしたと言うのかもしれませんが、それさえもあってはならない行動です。
他のスポーツの様にチャレンジ制度がない高校野球はこれまでも誤審は数え切れず、そのせいで甲子園に出られなかった高校さえあります。
人間のやることですからミスはある・・・でも審判も極力なくそうと懸命に努力しています。
自分のミスが子供たちの夢を奪い去ることを知っているからこそなのです。
今日のハーフスイングへの【何ごとかの発言・・・あるいは抗議】は、審判へのリスペクトがないと言えます。
また、3点リードを追いつかれた時、流れを変えようとしたのではないと思うが・・・水を補給し治療のタイム。
これも常勝チームには必要なテクニックなのか?
そうだとしたらおよそ・・・まさに勝てなくて良かったと言わざるを得ない。
敗れて泣き崩れる気持ちはわからんではないが、相手チームは整列していて審判員は整列するよう促しているのに・・・聞き入れようとせず。
自分達を敗ったチームへのリスペクトがない姿勢も、まさに普段から教えて正しておくべきである。
試合後、球場中がアウェイのようだったと話していた選手がいた。
そうだったと思う・・・それは弱いと言われたチームへの判官びいきだけではなかった気がする。
試合が進むにつれて・・・そんないくつかのシーンが目についた観戦者の素直な感情だったのではないか。
ひたむきに白球を追い、好投手の投球に必死に食らいつく高校生らしい姿勢に心を動かされた観戦者多かっただけに過ぎない。
ちなみに10回のライトへのライナー性の飛球は、フェアグランドでライトの選手のグラブにほんのわずかにかすっている。
落ちた場所がファールグランドだとしても、判定はフェアであるべきで県岐商のサヨナラ勝ちだった。
しかも落ちたボールは・・・白線上でこの結果からもフェアで県岐商のサヨナラ勝ちだったと言える。
ただ跳びついたライトの選手の身体が審判員の視野を遮り、あのファール判定になったと思うが・・・それも高校野球なのだ。
県岐商は【誤審】と抗議する姿勢も雰囲気も全く感じさせず、淡々と試合の進行に臨んだ。
そして正々堂々と勝利した。
これは決して横浜高校の生徒の努力を貶めるものではなく、勝利至上主義とみられた横浜高校の指導者への苦言である。
子供たちは懸命に頑張ったが・・・本来は大人が部活動は教育の一環であり、甲子園もその延長であると自覚すべきだった。
監督や学校側が事前に教えておくべきだったことが少し足りなくて、球場の雰囲気をアウェイにしてしまった。
子供たちには不幸だったが・・・。
蔦さんの言を借りれば【子供たちが得たものは大きく】・・・けっして不幸だと言う言葉はふさわしくなかったと、後(のち)に知るはずだ。
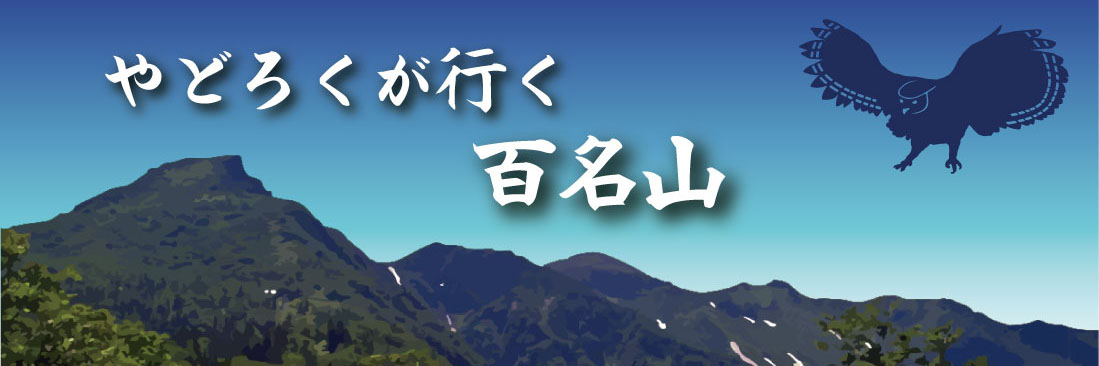


コメント