大斎原は【おおゆのはら】と読みます。
かつての熊野本宮大社があったところで、熊野川の水害で被害を受け遷宮をした跡地になります。
敷地内には駐車できないので、本宮大社からは歩いていきますが、せいぜい5分あれば到着します。
是非、車で乗り付けるなどの勝手な行動は控えてほしいものです。
ただ、キャンピングカーでは無理ですが、軽自動車程度の車両が敷地の奥の川原まで入り込んでいました。
川原に行くとしては、この道を利用できるのでしょうか?
あるいは他の道を利用して、川原に行ったのかもしれません。
目の前に現れる鳥居は高さ34m、幅は42mもあって日本一の大きさになります。
今年が25周年だそうですが、残念ながらコンクリートの建造物。

しかし鳥居をくぐった敷地内は霊験あらたかで、有名なパワースポットとして知られて訪れる人も多い。
中には石室が2基建立されていて、それぞれに神様が祀られています。
撮影禁止なので写真はありません。
誰かがいるわけではないので、撮ろうと思えば撮れますがモラルの問題です。
誰もいないと言うことは・・・ここで御朱印はいただけません。
本宮大社で一緒にもらうことになります。
本宮大社のお参りが済んだら、社務所で本宮大社の御朱印と一緒にいただくことが出来ます。
猿田彦神社もあわせてここでいただきます。
大斎原の御朱印は、今年なら鳥居建立25周年の綺麗な特別御朱印が頂けます。
ですが私は頑固に墨の黒い文字御朱印一辺倒です。

ところで熊野速玉大社でも那智大社でも、そしてこの本宮大社でもこの奇妙なカラスがシンボルとして掲げられています。
このカラスは八咫烏【やたがらす】と言い、神武東征の道案内として天照大神から遣わされたという神話が伝わっています。
ある人物に重ね合わせる神話もあるようですが、ウィキペディアでも調べれば神話も楽しくなると思います。
八咫烏に導かれた神武天皇は、樫原に到達して大和朝廷を起こすことになります。
八咫烏に使われる【咫】の字は、【あた】という長さの単位だそうです。
人差し指と親指を広げた、18センチほどの長さを言うそうです。
したがって八咫は18×8で144センチになるわけですが、この場合は【大きいカラス】を意味していると理解します。
功績が大きいカラスを巨大化した表現が、八咫烏なのでしょう。
今でも神様の使いとして神格化されシンボルになっているのです。
3本の足も奇妙ですが・・・天と地と人を表しているという説もあります。
韓国歴史ドラマフアンにはおなじみ・・・高句麗(現在の北朝鮮付近)の旗印に三足烏【さんぞくがらす】が必ず登場します。
スタイルはほぼ同一です。
古事記などには八咫烏の表現は観られず、中国の文化、韓国文化との融合で、平安朝あたりから見受けられる表現だそうです。

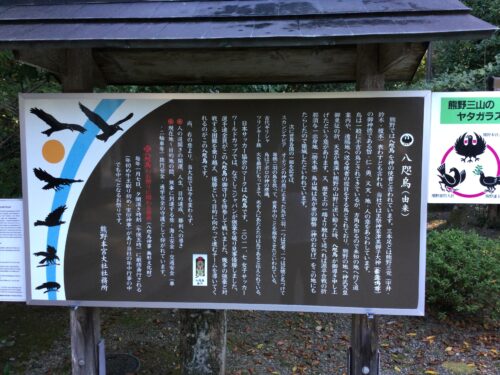
奈良への道がどの程度整備されているのか・・・情報がありませんでしたから、帰路は新宮への道を選択。
期待にたがわず整備された道で、快適に走れました。
熊野本宮から新宮市街地まで、30数キロですから1時間もかかりません。
新宮市に入ると市街地への途中に、道の駅【瀞峡街道熊野川】があり休憩としました。
この道の駅も多くの外国人がたむろしています。
船下りを体験できるので、それを楽しむ外国人が出発時間を待っているのです。
むかし高貴な方たちが熊野本宮大社をお参りし、続いて熊野速玉大社に熊野川を利用した船下りで向かったのです。
ですから熊野川も参詣の川の古道と呼ばれていて、世界遺産に登録されています。

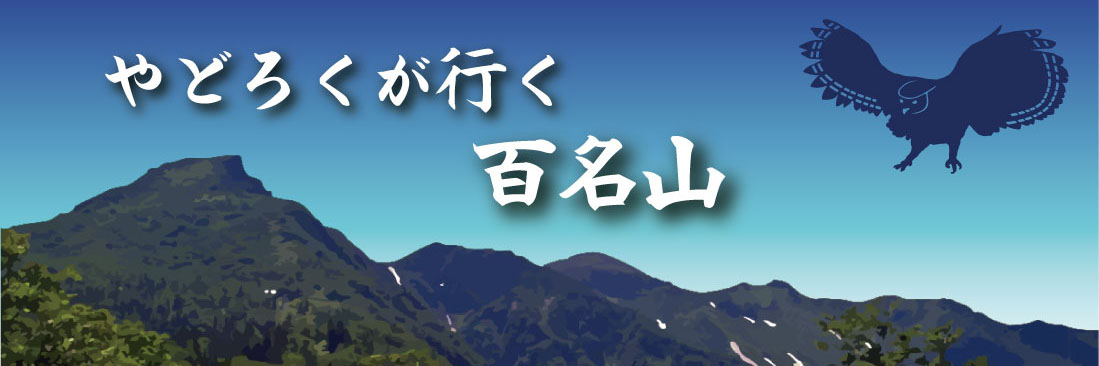


コメント